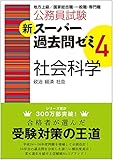法学検定2016、ベーシックとスタンダード
自分の法律に関する知識を客観的に証明するものが無いこと。
そして鍼灸マッサージ師でも法律や裁判の仕組みを理解せずに無茶苦茶なことを言う人もおり、そういう人たちに法律などを理解してもらうのに適当な検定試験がないか。
その2つの目的から法学検定を受けてみた。
「法学検定試験」は、公益財団法人日弁連法務研究財団と公益社団法人商事法務研究会が共同で組織した法学検定試験委員会が実施している、法学に関する学力を客観的に評価する、わが国唯一の全国規模の検定試験です。
詳しい内容はリンク先を読んでいただくとして、ベーシック〈基礎〉、スタンダード〈中級〉、アドバンスト〈上級〉とあり、要項(PDF)によればベーシックは法学部1年〜2年、スタンダードは2〜3年ぐらいのレベルだそうで、この試験に合格すると単位をくれる大学もあるらしい。
法学検定何も勉強してないのに受けないと単位消えるから受けなきゃいけないのさいあく
— 山﨑 知也 (@yamatomo0225) November 26, 2016
はい!法学検定スタンダード受かりました〜✌️4単位あざまーす✌️
— なつみ (@ntmaui1015) November 28, 2016
私の法律に関する知識は国家一種試験の教養試験レベル(技官で受けて、一次だけ通過)と、医事法規、特に無免許医療の判例、そして職業選択の自由に関する理解のために憲法判例百選を読んだ程度である。あとプロバイダ責任制限法関連か。

最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 (勁草法律実務シリーズ)
- 作者: 松尾剛行
- 出版社/メーカー: 勁草書房
- 発売日: 2016/02/25
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
あとは国民生活センターや消費者庁による、消費者契約法に関する判例解説を読んだ程度。
消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等(発表情報)_国民生活センター
なので私の法律知識はだいぶ偏っている。
もっとも法律専門職を目指すわけでもないので偏っていても構わないのだが。
ただ、私はトラブルを解決する、あるいは予防するために法律を学んでいるのではない。
業界の法秩序を変える(判例変更や人の健康に害を及ぼすおそれのある行為の明確化)ためであり、そのためには裁判所に判断してもらえる形でのトラブルが必要なのである。
そのためにはゼネラルな法知識も必要になってくる。
弁護士は法律紛争の解決・予防の専門家であって、紛争の起こし方を提案する商売では無いはず。
紛争の解決・予防のみを考えるならビジネス法務検定の方が実用的だろう。
と話がそれてしまった。
まあ、想定する対象者として法学部生を出しているので学術的な面が強いです。
で、検定の存在を知ったのは10月になってから。
ベーシックとスタンダード、一緒に受けると割引なので一緒に申し込む。
ベーシックの問題集はスマホアプリ、スタンダードの問題集は紙で購入する。
でもほとんど勉強できず。
電車通勤してないのでスマホで問題を解くのも不向きである。
そんなわけでほとんど対策もできずに本番。
仙台では約40名の受験。
民法の物権とか債権とか全くわかりません(汗)
私が民法でわかっているのは第90条と後見人、相続関係ぐらいである。
すでに解答は公表されていますので採点結果。
法学入門 7/10
憲法 13/15
民法 13/20
刑法 13/15
合計 46/60
過去のデータを見ると30〜36点で合格なのでベーシックは記入ミスなどがなければ合格確実。
憲法、民法、刑法が同じ13点ですが民法は20点あるのでいかに私が民法に弱いか、というのがわかりますな。
で、午後からはスタンダードの試験。
科目は「法学一般、憲法、民法、刑法」に加え選択科目が1科目。
選択科目は民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法、基本法総合(憲法、民法、刑法)
当初の計画は基本法総合を選ぶつもりだったんですが、民法は上述のとおりだし、憲法だって職業選択の自由や表現の自由に関する判例ばっかり読んでいて統治機構の細かいところなんて覚えていない。そんなことを午前のベーシックの試験で思い知らされた。
そんなわけで、以前に本人訴訟の本も読んでいるので民事訴訟法を選択することに。
で、採点結果
法学一般 8/10
憲法 11/15
民法 8/20
刑法 9/15
民事訴訟法 8/15
合計 44/75
過去のデータをみると合格ラインは40〜45点なので通知が来るまでは結果がわからない状態です。
でもこれで受かるのもなんだかな、という気もします。
---2016/11/29編集---
ツイートを埋め込んでいましたが、削除。
直接抗議は来てないのですが、ツイートのブログ掲載の事後報告にご不満なようでしたので。
なお、公開アカウントによるツイートの再利用などはツイッターの規約により了承済みとなっています。
ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、当社があらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)を当社に対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。ユーザーは、このライセンスには、Twitterが、コンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提に、本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利ならびに本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく、当該コンテンツを上記のように追加的に使用できます。
---(追記終わり)---
ちなみに民事訴訟法は私の場合、原告適格や裁判の土地管轄といったあたりが関係してきます。
本来なら手続きに関しては弁護士に任せるのが良いんでしょうけど、予め知っておかないと対応できないこともありますので。
冤罪が怖い人、陥れられそうな人、犯罪被害にあったときに警察の怠慢が許せない人は刑事訴訟法を勉強しても損はないかと思います。
@binbo_cb1300st 原則として警察は検察に事件を送致する必要があります(刑事訴訟法246条)。検察が起訴をせず、それが不当であれば、告訴者や告発者等(検察審査会法2条2項)は、検察審査会に審査を申立てることができ、一定の要件を満たすと起訴されます(同法41条の6)。
— QB被害者対策弁護団団員ronnor (@ahowota) July 24, 2014
@binbo_cb1300st まず、告訴・告発があれば、警察は犯罪の捜査をして(結論が起訴できないという場合でも)検察に送致しなければならないというのが原則です。検察に送致しないようであれば、警察に「刑事訴訟法246条があるのではないですか?」とお聞きになってはいかがでしょう。
— QB被害者対策弁護団団員ronnor (@ahowota) July 24, 2014
@binbo_cb1300st あと、「刑事訴訟法242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」も使えるでしょう。
— QB被害者対策弁護団団員ronnor (@ahowota) July 24, 2014
行政との交渉が必要な場合もあるので行政法の理解もあったほうが話は進めやすいかも。
というわけでちゃんとそこら辺を勉強しておきたいのでスタンダードが落ちても気にしないことにしよう。